今回は、GoProのロードバイクへのマウント方法について考えてみます。
ライドの動画を撮影するのにGoProをどのように装着して撮影するのが良いのか・・・
結構迷う方も多いのではないでしょうか。
- GoProなどのアクションカムを使ってライド撮影したい人
- ライド撮影をするのにカメラをどこに装着するか迷っている人
- 装着する場所で映像がどのように変わるのか知りたい人
- カメラの装着方法について知りたい人
- 装着場所によるメリットやデメリットが知りたい人
GoProの取り付けは2パターンある
 よすけ
よすけ私もGoProの取り付け位置はどこが良いのか、かなり試行錯誤してきました



今も試行錯誤は続いていますが、私が試した取り付け方法のいくつかをご紹介します!
今までいろいろなパターンの装着方法を試してきましたが、ライド動画撮影のパターンを大きく分けると2つのパターンがあります。
- ロードバイクに装着するパターン
- 自分の身体に装着するパターン
この2つのパターンのどちらかで動画撮影していると思います。
これはどちらが良いかというよりは、どちらが好みかによるのかなという気がします。
以下では、それぞれのパターンでいくつかのパターンをご紹介します。
Youtubeの動画でも同じテーマの動画をアップしていますので、この記事と合わせてご覧いただくと理解しやすくなると思います。
ロードバイクにカメラを装着する方法
自転車そのものにカメラを据え付ける方法の共通の特徴としては、走行映像が比較的安定しており、映像が見やすいという点です。
GoPro Hero9 Blackの手ブレ補正機能であるHyperSmoothは非常に優秀です。
手ブレ補正モードONにして、さらにブーストONで撮影するとほとんど手ブレしない映像が撮影できます。
その1)サイコンマウントの下へのマウント




上の写真のようにサイコンマウントの下にカメラを逆さまに取り付ける方法です。
撮った映像はこんな感じになります。


このマウント方法のメリット・デメリット
このマウントの特徴は、ハンドルより下の位置に装着するので視点がかなり低い映像になります。
そして、映像には自分のロードバイクは映らず遮るものは何もない映像となります。
- マウントがハンドルより下にあり、ぱっと見で目立たないため撮影している感がない
- 広角で撮影すると、視点が低い分スピード感のある映像が撮れる
- 自分のロードバイクが全く映らないので、ライド感が乏しい
- 映像は前方の景色が流れているだけの単調な映像になりがち
- 装着しているカメラが自分の目からは見えにくく、カメラ操作がしにくい場合がある
ハンドルの下にマウントするため、目立たない点は大きなメリットです。
たとえばグループライドでの撮影、グループライドでの撮影などでは、先行する人を撮ると相手も撮影されている感が少ないため、カメラの前で自然な感じで撮影できたりします。
レースなどでは、臨場感あふれる撮影になるのも良い所ですね。
また、サドル下にもう一つGoProをマウントして後ろの様子も撮影して変化をもたせるなどのバリエーションも考えられます。
そうすれば、単調な映像をカバーすることができますので、このような使い方を考えている方にはおすすめできるマウント方法です。
しかし私のように、ソロライドが中心のライドには、他の仲間がロードバイクに乗って写っていないと自転車でのライド走行であることが画面だけでは分かり難しいかもしれません。
撮れる映像は景色が流れる景色だけとなってしまい、単調な映像の連続になってしまいます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ソロライドなどではあまりおすすめできないマウント位置かも…
同じように、ロードバイクのハンドルにマウントする場合も同様です。
サイコンマウントの下に装着するよりカメラが目立ちますので、「撮影している感」は出てしまいますね。


ハンドルへの取付けでは真ん中にはとりつけられないため、この場合は左よりの画像になっているのも特徴。
なお、サイコンとGoProの取り付けについては、レックマウントのこちらの商品を使用しました。
各種のサイコンアダプターがついているので、サイコンを買い替えても付属アダプターを取り替えるだけで対応できます。
レックマウントは少々お値段が高いものが多いですが、その分作りはしっかりしており、剛性が高く走行中にずれたり外れたりすることがなく、信頼性の高い商品が多くおすすめです!
ハンドルマウントはGoPro純正のマウントを使用しました。
このマウントは、横方向にカメラを回すこともできます。
カメラを横にして横に流れる景色を撮影することもできるので便利です。
その2)ステムのトップキャップの位置にマウントする




ロードバイクのステムのトップキャップのところにアダプターを付け、そこにカメラをマウントする方法です。
映像はこんな感じ。


このマウント方法のメリット・デメリット
このマウント方法の特徴は、視点がハンドルよりも高く自分の自転車の一部が映像に映ること。
画角にもよりますが、ハンドルや自分の手などが映像に映ります。
- 視点がハンドルより高くライド感が出る
- 広角での撮影では景色の流れとともに自分の手やハンドルが映り自転車に乗っている臨場感が出る
- 手前に映る手やハンドルが影響して、広角であればあるほど景色が流れるスピード感を感じる
- 自転車に固定した撮影で画像が自転車とともに傾くので、人によっては画面酔いする場合がある
- 広角でないと手前の手やハンドルの画像が大きく映るので気になってしまう場合もある
このマウント方法は、自転車への固定マウントの中では、ハンドル操作、STIの操作なども一緒に映像に入りますので、ライド感がとてもよく出ることです。
デメリットの映像が自転車とともに傾く点については解決策があります。
それはアクションカメラの水平維持機能を使うことです。
水平維持機能があるアクションカメラなら画像が傾くことがなく、安定した映像を撮影することができます。
ただし、マウント方法によっては、カメラが小刻みに振動を拾ってブレた映像になるケースもあります。


写真のように、カメラとステムのトップキャップアダプターの間に延長アダプターを装着して高さをだそうとすると、カメラの重量によっては延長アダプターが自転車の走行振動を拾ってしまい、アクションカメラの手ぶれ補正機能のキャパを越えて、ブレを吸収できないということがありました。
ただし、最近のアクションカメラは手ぶれ補正機能がかなり進化していますので、このような装着方法でもブレのない映像を撮影できる可能性もあります。



ライド感や画面の安定度からみて、自転車に取り付けるならこの方法がおすすめです。
自分の身体にGoProを取付ける(マウントする)方法
GoProを自分の身体の方にマウントすることで、自分の身体の動きに合わせた動きのある映像を撮ることが可能になります。
時として、体を動かすことで映像が大きく揺れる場合もあります。これを臨場感と捉えるか、余計な揺れととらえるかは見る人によって違うと思いますので、良いとも悪いとも言えないところではあります。
また、自転車を降りても自分の身体に付いていますので、そのまま撮影すれば、ライド以外の様子も撮影できるという点が大きな特徴です。
その3)ネックマウントを使う


GoProをネックマウントに取り付けて、写真のように首にネックレスのようにぶら下げる方法です。
映像はこのような感じ。


このマウントのメリット・デメリット
首にカメラをかけての撮影になるので、視点は自分の顔にかなり近いところから撮影できます。
つまり自分の視線にかなり近い映像になるということ。
広角での撮影であれば、カメラレンズの上下の撮影方向によっては自分の体の一部も映像に入れ込むことができます。
いわば撮影者の目線での映像を撮ることができる点が特徴でしょう。
- 自分の目線に近い映像が撮影できるので、撮影中にできあがりの映像を想定しやすい。
- ネックマウントの仕様にもよりますが、首にひっかけるだけのものであれば脱着が容易です
- 自分の体に装着しているのでライド場面以外の撮影も継続して可能
- 首にぶら下げる感じになるので、ライド中の前傾姿勢ではネックマウントが揺れて映像が揺れる
- 特にライド中は首にカメラをぶら下げることで首に重さが乗り、首や肩が凝ったり疲れたりする
このマウントの最大のメリットは、首に引っ掛けるだけですので、あっという間に脱着ができる手軽さが最大のメリットです。
私の場合、この手軽さが非常に気に入って、このマウントを利用することも多いです。
ただし、首に引っ掛けているだけという点がデメリットにもなってしまいます。
前傾姿勢をとると下の写真のように身体が揺れる度にカメラが前後に振り子のように揺れるのです。


このため、たとえ強力な手ブレ補正でブレを補正できても、ブレ補正のキャパを越えてしまって撮影した映像が大きく揺れてしまう映像になってしまことがあります。
ヒルクライムなどで立ち漕ぎなどをするとカメラがブランブランと前後にゆれて、映像が上下に激しく揺れてしまう場合が結構あります。
画面全体が揺れたような映像になるので、画面酔いしやすい方にはちょっと耐えられない映像になってしまいます。
撮影している時にカメラが揺れ始めるとかなり気になったりします。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
画面全体がグラグラ揺れるので、立ち漕ぎや激しい動きに映像がついてきてくれず、ヒルクライムなどではおすすめできない方法かも
さらに、カメラの重さが首に集中してかかるので、首にかかる重さの負担が結構大きい。
とくにロングライド後に首や肩が凝ってしまっていることもしばしばあります。
その4)チェストマウントを使う


身体に付けるもう一つの方法は、チェストマウント用のハーネスを身に着けてGoProをマウントする方法です。
伸縮性のあるしっかりしたハーネスを体に装着するのでガッチリとカメラを固定した装着方法です。
映像はこんな感じになります。


このマウントのメリット・デメリット
視点は胸からみぞおち辺りにカメラがあるので、ネックマウントに次いで高い視点からの映像になります。
広角の撮影であれば、上の写真のようにかなり広い範囲で自分の体の一部やロードバイクが映ります。
- 映像には自分のロードバイクや体の一部(場合によっては膝くらいまで)が映り込むのでライド感がかなり伝わる映像になる
- ハーネスでしっかりカメラを固定するので、ネックマウントのような揺れは発生しない
- 胸元にカメラがあるので、カメラ操作がしやすい
- ハーネスで体に固定するため、体に締め付け感がある
- カメラの方向を固定すると、ライドしている時と自転車を降りた時のアングルを変えないと意図とは違う方向を映した映像になる
- 自分が撮りたい映像を撮るためには、場面場面でこまめなアングルの調整が必要な場合がある
- 体の動きが激しい場合は、ブレ補正のキャパを越えてしまう場合もある
映像そのものは、ネックマウントに比べるとはるかに安定した映像が撮影できます。
この撮影方法はロードバイクのハンドル全体や腕、場合によってはペダリングする膝あたりまで映るので、臨場感あるライド映像が撮れるという点で優れています。
ただし、チェストマウントで安定した画像を撮ろうとすると、前傾姿勢でライドしているときと自転車を降りてあるくときとでは、カメラのアングル(撮影方向)を調整しなければなりません。
例えば、前傾姿勢でライドしている時の角度のままで自転車を降りると、カメラは上を向いたままになるのでカメラを体の正面に向け直すという調整が必要になります。
これがかなり面倒くさいし、調整を忘れてしまうこともしばしばあり、ライド以外の場面で撮影した画像が空ばかり映しているなんていうこともあります。
また、体につけるマウント方法に共通して言えることですが、自分の体の動きに応じた映像となるため、画面酔いや出来上がった映像を意識した動きをする必要があります。
あまり映像のことばかり気にしてライドしていると、ライドそのものが楽しめなくなったりしてはサイクリングの楽しみをスポイルすることにもなりかねません。



本末転倒になってしまうので気をつけたい所ですね
それぞれのマウントの個人的評価
私個人の独断と偏見でそれぞれのマウント方法を評価すると以下の表のようになります。
| マウント方法 | 取り付けやすさ | 映像の臨場感 | 画面の安定性 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
| サイコン下マウント | △ | △ | ◎ | ◯(△) |
| トップキャップマウント | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
| ネックマウント | ◎ | ◎ | △ | ◯(△) |
| チェストマウント | △ | ◎ | ◯ | ◯ |
表をみていただくとわかるのですが、映像におけるライドの臨場感は大事ではありますが、私の場合はできるかぎり画面酔いしない安定した映像を重視する傾向があります。
チェストマウントの臨場感も捨てがたい魅力はありますが、トップキャップマウントの映像の安定性にはかなわないというのが、私個人の結論です。
そこで、次に私のトップキャップマウント方法をご紹介します。
私のアクションカメラのマウント方法


このマウント方法のポイントは、GoProの脱着を簡単にするために、トップキャップマウントに直接GoProを装着するのではなく、クイックリリースを装着している点です。
もちろん、GoPro純正のアダプター用のマウントでも良いのですが、個人的にはあまり格好良くないと思いますので、Ulanziのクイックリリースを利用しています。
以下で具体的なマウント方法を説明します。
| 取り付け位置 | 取付けるアダプター | 取付のポイント |
|---|---|---|
| ステムのトップキャップ | レックマウント トップキャップマウント 商品名:REC-MOUNTS トップキャップマウント タイプ1 Top Cap Mount for GoPro(ゴープロ)HEROシリーズ用 ステム/前方撮影に [REC-B09-GP] |
|
| トップキャップマウントにはクイックリリースを装着 | Ulanzi クイックリリース
商品名:Ulanzi Gopro 三脚 マウント クイックリリースマウントアダプター マウント アダプター クリップ 簡単取付 DJI Osmo Action/insta 360/Gopro Max/Gopro Hero 8 7 6 5 アクションカム ウェアラブルカメラ用 アクセサリー |
|
このUlanzi クイックリリースを付けることで、GoProの脱着が非常に簡単にできるようになります。
GoPro純正のアダプターもしっかりと装着できるという点では一緒ですが、アダプターそのものが大きく、見た目にあまり格好が良いとは思えません。
その点このクイックリリースは小型で、純正よりも脱着がしやすくスマートです。
しかも磁石も入りかみ合わせもしっかりしているので、走行中にガタつく心配はまったくありません。
実際使用していてガタついたことはまったくありません。
クイックリリースを使うことで、自転車を降りたときに気軽にGoProを取り外して三脚に付けて撮影ができるのも大きなメリットです。
立ち寄りスポットなどで自転車からGoProを取り外してそのまま撮影することができれば、撮影のバリエーションも広がります!


ミニ三脚なら何でも良いと思いますが、Ulanzi クイックリリースには三脚用のアダプターも同梱されているので、GoPro用のミニ三脚でなく、ネジ式の三脚がおすすめです。
写真の三脚は同じUlanziからでているミニ三脚で、クイックリリースが三脚のネジ部と直径がほぼ同じで見た目がスッキリします。
私はUlanzi のこちらのミニ三脚を利用しています。
自由雲台のようになっているので、角度を簡単に自由に変えることができるので非常に重宝します。
アクションカメラの撮影時間とメディア容量について
もう一点。



私はアクションカムをライド中撮影しっぱなしにすることが多いんです。
撮影チャンスはいつ巡ってくるかわかりません。
思わぬ時にとても良い映像が撮れる時もあります。
しかし、撮影しっぱなしにすれば、当然ですがバッテリーと記録メディアの容量がネックになってきます。
そこで、私は下の写真のようにモバイルバッテリーで撮影しています。
そして、メディアの容量は512GBのマイクロSDカード
これで、8時間程度の撮影が可能です。
ただし、使用するアクションカメラが、付属のバッテリーをはずしても給電撮影が可能なものでないとうまくいかないのでご注意を。
GoProのような給電しながらの撮影が可能なアクションカメラであれば、1日のライドはこれで撮りっぱなしにできます。
カメラに内蔵するバッテリーを外すことで熱暴走も防ぐことができるというおまけつきです。
ただし、録画した動画を編集する際は、長時間の撮影動画からいいところを抜き出す作業がかなり面倒くさいことにはなります。
ですので、慣れてくると単調になりがちな撮影シーンはあえて撮影しないなどの工夫をするようになります。
モバイルバッテリーは、トップチューブに取付けているフレームインナーバッグに入れています。


モバイルバッテリーを持ち歩いて撮影する場合はハンドルかトップチューブにバッグの装着が必要になり、バッテリーを含めるとそれなりに重くなります。
ヒルクライムやロードバイクを出来る限り軽くしたいという方には不向きな方法です。
私の場合は、ロングライド中心で重さに対しては比較的気にしないで乗るタイプなので、この方法をとっています。
実はこのモバイルバッテリーを使う撮影方法が、GoProを身体に付けないもうひとつの要因でもあります。
容量の大きいモバイルバッテリーはそれなりに重さがあるので、ウェアのポケットに入れるのは濡れることも考えると避けたい。
リュックやポーチをそのためだけに担ぐのもできれば避けたい。
そこで、自転車にバックをとりつけてGoProをマウントするという方法に行き着いたという背景もあります。
人によってマウントの選択肢の優先順位は違ってくると思いますので、どなたにでもおすすめできるというわけには行かないかもしれません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ご紹介した一部でもご参考になるところがあれば嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
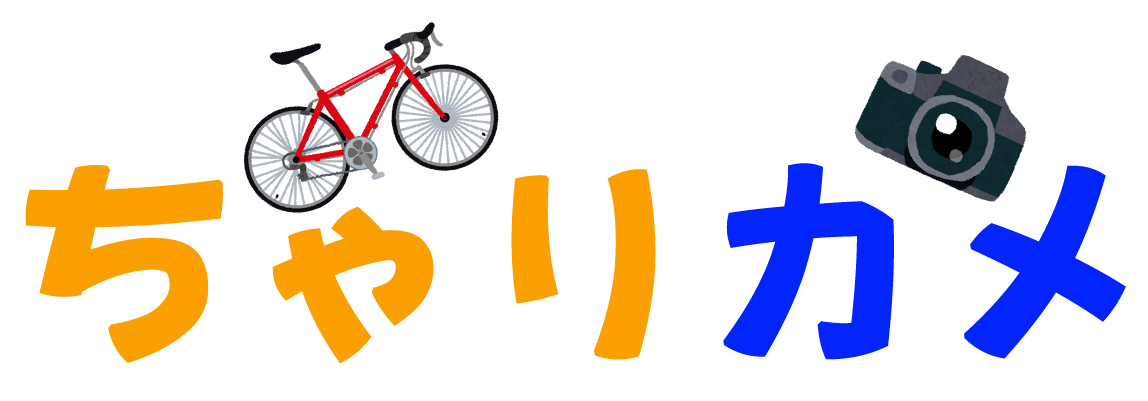

















コメント