こんにちは。
よすけです。
今回は、ロードバイクで持ち運ぶカメラのお話です。
カメラのお話は、何回かこのブログで書いていますが、ここでは私が使っているミラーレス一眼とレンズのお話をしたいと思います。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://chari-came.com/photo-camera target=]
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://chari-came.com/camera-bags target=]
私が現在使っているミラーレス一眼カメラは、富士フィルムのX-S10です。
私は、過去にいろいろなカメラを使ってきていますが、今、このカメラを使っている理由とおすすめのレンズについてお話します。
X-S10を選んだ理由〜過去に使ったカメラと比較

私が過去に使っていたカメラと比較してみましょう。
私は、このX-S10を使う前は、センサーサイズが同じAPS-C機では、ソニーのα6600を使っていました。
その前は、センサーサイズはマイクロフォーサーズという一回り小さいものになりますが、オリンパスのOM-D E-M1 MarkⅡを使っていましたので、この三機種を比べてみたいと思います。
大きさ・重さの比較
| 項目 | 富士フィルム X-S10 |
ソニー α6600 |
オリンパス OM-D E-M1 MarkⅡ |
| 有効画素数 | 2610万画素 | 2420万画素 | 2037万画素 |
| 大きさ (幅×高さ×奥行き) |
126×85.1×65.4mm | 120×66.9×69.3mm | 134×90.9×68.9mm |
| 重さ ()内はバッテリー・メモリカード含 |
415g (465g) |
418g (503g) |
498g (574g) |
有効画素数
スペック上の数値では、X-S10が一番です。
感覚的にもX-S10の静止画は、髪の毛一本一本まで解像しているようなキメの細かさを感じます。
ただし、センサーサイズがマイクロフォーサーズであるOM-D E-M1は、センサーサイズの割に画素数が多い点も注意です。
ハイレゾ撮影などではかなり精細な写真がとれます。
では、α6600は画質が悪いのかというとそうでもなく、ぱっと見で比較して、どれがどれかと聞かれてもわからないくらいの差であることは確かです。
大きさ
ロードバイクでカメラを持ち運ぶのであれば重要な要素ですね。
一番コンパクトだと言えるのはα6600でしょう。
X-S10はファインダー部分があるため、高さがα6600に比べて18mmも高いです。
ただし、奥行きはX-S10が一番薄いですね。
重さ
こちらもロードバイクでカメラを持ち運ぶ際の重要ポイント。
これは、X-S10が最軽量。
とくにバッテリーとメモリーカードを含んだ重さでは、唯一400g台をキープしています。
α6600は、バッテリーが大型化したことで、コンパクトな割に重くなっています。
OM-D E-M1は、当時のフラッグシップ機だったこともあり、大きさ、重さともに他の2機種には負けてしまいます。
しかし、数値だけでは判断できない部分もあります。
X-S10とOM-D E-M1は、ファインダーがレンズの光軸上に位置していて、一眼レフと同じようにカメラらしい外観です。
一方、α6600は、ファインダーがボディの左上にあるため、一眼レフ機とは違った外観になります。
外観と大きさ・重さのバランスで言うと、私個人は、静止画を撮るためのカメラとしては、カメラらしい外観をしたX-S10やOM-D E-M1の方が好みです。
性能面の比較
| 項目 | 富士フィルム X-S10 |
ソニー α6600 |
オリンパス OM-D E-M1 MarkⅡ |
| AF ()内は測距点数 |
位相差+コントラスト (117点) |
位相差+コントラスト (425点) |
位相差+コントラスト (121点) |
| 連写機能 | 30コマ/秒(電子シャッター) 8コマ/秒(メカニカルシャッター) |
11コマ/秒 | 60コマ/秒(静音シャッター) 15コマ/秒 |
| 手ブレ補正 ()内は補正段数 |
5軸最大6段分 | 5軸最大5段分 | 5軸最大6.5段分 |
| 動画(最大記録画素数) | 4K30fps | 4K30fps | 4K30fps |
| 防塵防滴 | ✕ | ○ | ○ |
| 価格(Amazon) (レンズキット価格) |
118,800円 (129,800円) |
126,200円 (196,000円) |
105,000円 (147,780円) |
| 発売日 | 2020年11月 | 2019年11月 | 2019年2月 |
オートフォーカス(AF)
α6600はスペック上では一番です。
AFの速さやピタッと合う感覚は、さすがソニーという感じで、X-S10より上です。
しかし、実際の使用感から言うと、X-S10もピントは0.02秒という高速のAFでピントの合焦に関してのストレスは全くありません。
昔は、富士フィルムのカメラのAFは遅いというイメージがあったのですが、X-S10を使ってみて、AFが遅いと感じたことはありません。
それは、OM-D E-M1も同じで、測距点の多さはAFのポイントですが、ソニーのカメラのAFの速さは抜群ですが、実用面で他の2機種がストレスを感じるという程の差はないと思います。
連写機能
OM-D E-M1の静音シャッターでのスピードは桁違いです。
さすがフラッグシップ機だっただけのことはあります。
X-S10はメカニカルシャッターで8コマ/秒ですから早いとは言えないレベルでしょうか。
その中間がα6600という感じです。
ただ、私個人は風景などの撮影が多いため、連写はあまり使いません。
でも、動物や鉄道など、動くものを撮る方にとっては無視できない性能になると思いますのであえて上げてみました。
手ブレ補正
手ブレ補正が優秀なのはOM-D E-M1です。
X-S10も6.5段分の優秀な性能を持ってはいますが、狙った被写体にビタッと張り付いて微塵もぶれない、という感覚はOM-D E-M1ならではの感覚でした。
X-S10も静止画での手ブレ補正の効き方はとても優秀です。
ピタッと止まるという意味ではOM-D E-M1に準ずる感覚です。
ただ、動画撮影における手ブレ補正機能をどう見るかは、撮影方法によって見方が違ってきます。
ジンバルを使った動画撮影においては、効きが弱いといわれるソニーのほうが扱いやすいんです。
ジンバルなしの手持ちの動画撮影だとOM-D E-M1がNo.1でしょう。
少しぐらいの歩きながらの撮影でも、画面がぶれないのは凄いです。
ジンバルに載せているのではと思わせるような映像が撮れることもあります。
X-S10は、ブレ補正のキャパを超えるとカクっと動くので、手持ちの撮影は正直カクカクしてしまい、ブレない撮影はできません。
動きながらの撮影よりも自分は止まって撮影するような場面ではピタッと止まるので、能力を発揮します。
動画撮影においての総合的な手ブレ補正の使い勝手の良さは、ジンバルに載せたα6600がベストだと思います。
動画撮影
これはスペック上は、三機種とも4Kで30fpsの撮影が可能で、普通に使うには差がありません。
OM-D E-M1は私は持っていたときは、log撮影はできなかったのですが、現在はファームウェアのアップデートでできるようになったようです。
動画撮影の機能面では映像作品を撮るなどの本格的な動画制作でないなら、ほとんど差はないといって良いでしょう。
防塵防滴
X-S10のみ防塵防滴ではありません。
しかし、ライドで写真を撮る場合、ミラーレス一眼の場合は、以前のブログでご紹介したとおり、ボディバッグなどに入れて持ち運びます。
雨が降っても、バッグに入れてしまえば問題はありません。
撮影はできなくなりますが、これは高級コンデジなどを持ち運ぶときも同じです。
また、防塵防滴機能は、完全に塵や水を防ぐということではなく、あくまで設計上中に水滴や塵が入ってこないように設計してあるという意味なので、塵や水滴が完全に入り込まないということではない点も注意が必要なのです。
価格
ボディのみで価格が安いのはOM-D E-M1ですが、発売日が一番古く、レンズセットでの購入となるとX-S10より高くなります。
α6600はボディのみもレンズセットも一番高い。
X-S10は、発売日が一番新しいにも関わらず、ボディのみ、レンズセットともにリーズナブルな価格です。
X-S10のスペック上のバランスの良さ

こうやってスペックで比較してみると、過去に使っていたカメラと比較して、数値上X-S10が大きく秀でたカメラということではありません。
私が使っていたカメラと同等か少し劣る部分もあるくらいです。
スペックでX-S10を選ぶ理由をあえて言うのであれば、大きさ、重さ、性能、外観と価格のバランスの良さです。
軽量コンパクトでかつ基本機能に何の不満もないリーズナブルなカメラらしいカメラであるということ。
これは、ロードバイクで持ち運ぶためのカメラとして、ベースになる重要なポイント。
ただし、それだけでは何かインパクトに欠けるし、別に他のカメラを使い続けていてもいいんじゃないかとも思いますよね。
私がX-S10を選んだのは、このバランスの良さに加えて、X-S10にしかない魅力もあるからです。
X-S10にしかない魅力
操作性

今までの富士フィルムのカメラって、軍艦部にやたらにダイヤルが付いているけっこう「癖の強い」カメラという印象が強かった。
シャッタースピード、ISO感度、露出補正などのダイヤルがついており、結構難しそうで厳つい印象を醸し出してました。
カメラ好きにはたまんない魅力でもあったのですが。
ところがX-S10は、いわば初心者や他のカメラを持っている人が普通のカメラとして操作できるようなモードダイヤルがメイン。
富士フィルムどくとくの設定ではなく、モードダイヤルの操作でサッと撮影できるんです。
まあ、他のメーカーのカメラを持っている人にとってはあまり実感できないところではありますが・・・。
色再現
富士フィルムはもともとフィルムメーカーであったこともあり、発色に強いこだわりを持って商品開発を行っています。
「人が見たときに心地よい色」の再現を目指しており、色だけでなくグラデーションなどの表現にもこだわっています。
その象徴といえるのが、富士フイルム創業80年のノウハウが注ぎ込まれた「フィルムシミュレーション」の搭載。
X-S10は、18 種類ものシミュレーションを使い分けることができます。
通常、カメラをある程度使いこなしてくると、写真をRAWというデータで撮影して、Lightroomなどのソフトを使って「現像」を行い、写真を完成させる人が多くなります。
しかし、富士フィルムのカメラの場合は、この「フィルムシミュレーション」で撮ったそのままのJPEGの画像データが美しく、加工などせず撮って出しでも十分完成されているのです。
他のカメラから富士フィルムのカメラに移る人は、たいていこの色味、色の再現性にやられて移ってきます。


上の2つの写真もJPEGの撮って出し。
PROVIAというスタンダードなフィルムシミュレーションでの撮影です。
加工は一切していません。

X-S10は、フィルムシミュレーションのダイヤルが、軍艦部の左側に配置されており、手軽に「フィルムシミュレーション」のモードを変えて撮影して、自分の好みの色味を探していくこともできます。
画質
画質を左右するのは、カメラのイメージセンサー。
富士フィルムのカメラは、フラッグシップの上位機種とその下のラインアップの中位機種のカメラでもセンサーが同じものを使っています。
X-S10の上位機種はX-T4というフラッグシップ機。
ボディだけでも196,000円(Amazon 2021年8月時点)します。
もちろん、機能や性能面ではプロ仕様として十分通じるカメラで値段相応の価値はありますが、X-T4で撮ってもX-S10で撮っても、センサーや画像処理エンジン(X-Processor 4)は全く一緒なのです。
だから、出てくる写真の画質は全く一緒。
出来上がった写真は、X-T4で撮ったのかX-S10で撮ったのかは全く見分けが付かないので、出来上がった写真だけのレベルで言えば7万円以上の価格差があるなんて想像もつかないでしょう。
X-S10は持ち運びに最適のカメラ
このような上位機種と同等の性能を搭載しながらも、リーズナブルな価格で手に入れる魅力をもったカメラが、X-S10です。
しかも小型、軽量。
ロードバイクで持ち運ぶミラーレス一眼としては、非常に魅力的なカメラだと思います。
富士フィルムのミラーレスカメラをお持ちの場合はボディのみ、はじめて富士フィルムのカメラを買う方はレンズキットでの購入がおすすめです。
参考価格:118,800円(Amazon、カメラのキタムラ)
参考価格:128,700円(カメラのキタムラ)
ロードバイクで持ち運ぶ場合のおすすめレンズ3選
X-S10は、一眼カメラですから、レンズは別に買う必要があります。
富士フィルムのブランドのフジノンレンズは、80年以上の歴史があり、レンズとしても世界中から高い評価を受けています。
富士フィルムのカメラを初めて購入する場合は、上のレンズキットでの購入して、慣れてから他のレンズを購入するというのがスタンダードな考え方でしょう。
でも、ミラーレス一眼の魅力は、性能の良いカメラに明るいレンズ(F値の低いレンズ)をつけて、ボケを生かした写真が撮れること。
であれば、ボディとレンズを別々に購入するのもありだと思います。
X-S10は、小さなボディであることが魅力ですし、そのボディに大きなレンズをつけたのでは、ロードバイクで持ち運ぶのは嫌になってしまうかもしれません。
そこで、ロードバイクで持ち運ぶのにピッタリな比較的コンパクトなレンズを、私が持っているものの中から3つ選んでみました。
XF35mmF1.4 R
参考価格:59,000円(Amazon)
富士フィルムのカメラはAPS-Cのセンサーサイズですので、35mmカメラ換算で53mm相当の単焦点レンズ。
知る人ぞ知る、描写力で富士フィルムの「神レンズ」と呼ばれている単焦点レンズです。
しかもコンパクト。
開放値がF1.4という明るいレンズで、大きなボケを作って雰囲気のある写真を撮ることができます。

ロードバイクの後輪に寄ってピントを合わせて、あとはなめらかにボケていくように撮っています。
F1.4の明るさを生かしてボケを使えばこのように立体感のある写真を撮ることができます。

F8あたりまで絞れば、風景もしっかりと撮れます。
よくカメラの構図や画角の感覚をつかむのに、最初は50mmのレンズで練習しろ、と言われますが、まさにこのレンズは最初の単焦点レンズにはうってつけのレンズです。
このレンズは、ピントはレンズ群を動かす「全群繰り出し方式」を採用しているため、ピントを合わせるたびにジジッ、ガガッと音がします。
よく、このレンズはAFが遅いなどと言われますが、私個人の感覚ですが、AFのスピードが遅いとは思いませんでした。
ピントを合わせるたびに音がするのでそういう感じがするのかもしれませんが、ピント合わせの速度はステッピングモーターの無音のAFとあまり変わらないと思います。
ただ、音のせいで、動画撮影などでは、ピント合わせの音が入ってしまうので向いているとは言えません。
参考価格:44,055円(カメラのキタムラ)
XF23mmF2 R WR
参考価格:47,020円(カメラのキタムラ)
こちらは、35mm換算で35mmの焦点距離をもつ広角の単焦点レンズです。
重さが180gしかなく、スナップ撮影などに最適です。
ただ、画角の35mmというのは、人の目で見たときの画角に非常に近いので、何も考えないで撮るとつまらない写真になりがち。
結構難しい画角です。

風景などは、このように結構自分の目で見た景色とあまり変わらないので、インパクトのある写真って意外と撮れないものです。

まあ、上の写真はあまりいい作例ではないかもしれませんが、写真は引き算とも言われるように、主題(上の写真の場合は空)を大きくとって、他のものをできるだけ排除していく工夫が必要かもしれません。
ただ、このレンズは軽くてコンパクトでF2の明るいレンズなので、もう一本レンズを持ち運べるのであればスナップや旅写真などには重宝しそうです。
また、ステッピングモータのピント合焦が静かなので、動画撮影などにも向いています。
F値が1.4のXF23mmF1.4 Rというレンズもあるのですが、値段が高く(99,500円 Amazon)、写真の腕が上達したら購入というレンズのような気がします。
こちらのF2のレンズはその半額(49,000円)で購入できるので、リーズナブルです。
XF18-55mmF2.8-4 R OIS
参考価格:57,300円(Amazon)
最後のレンズはズームレンズ。
35mm換算で27-82.5mmの標準ズームです。
このレンズは富士フィルムのカメラのキットレンズという位置づけなのですが、非常にクオリティの高いレンズです。
通常、キットレンズのF値は、F3.5-5.6といった比較的暗めのレンズが多いのですが、このレンズのF値は2.8-4という明るさがあります。
とくに最大開放値がF2.8なので、そこそこボケてくれますし、レンズ内手ブレ補正も付いているので、X-S10と合わせると6段分の手ブレ補正が実現します。

広角で絞って撮れば、解像度の高い写真が撮れます。

望遠側で撮ってもF4という明るさでそこそこボケて美しい写真を撮ることができます。
このレンズはキットレンズと言いましたが、単体でも正式に売り出しており、入手しやすい万能レンズです。
ただ、富士フィルムのカメラを初めて買う方なら、最初からキットレンズとして買うほうがお得です。
参考価格:168,000円(カメラのキタムラ)
まとめ
以上、ロードバイクでカメラを持ち運ぶ際のおすすめミラーレスカメラ、Fujifilm X-S10と、合わせて使いたいレンズ3つのご紹介でした。
Fujifilm X-S10というカメラの魅力は、
- 色味、色再現性は、他社のカメラに比べて非常にすぐれている
- 中級機であっても、センサーや画像処理エンジンに妥協はなく、上位機種と変わらない画質の写真が撮れる
- 軽量、コンパクトで、操作性に優れており、今までの富士フィルムカメラのようなとっつきにくさが払拭されているので初心者や他社からの移行でも使いやすい
という点です。
また、レンズ群もXFシリーズのレンズは、今回ご紹介したレンズ以外でも評価の高いレンズが多く、高性能で高画質なレンズが多くあります。
コンパクトで、X-S10との相性も良く、ロードバイクで持ち運ぶときに持っていきたいレンズもまだいくつかありますが、追々ご紹介していければと思っています。
いかがでしたでしょうか。
この記事が、ロードバイクで持ち運ぶカメラでお悩みの方の少しでもお役に立てたら嬉しいです。
引き続き「ちゃりカメラ」をよろしくおねがいいたします。
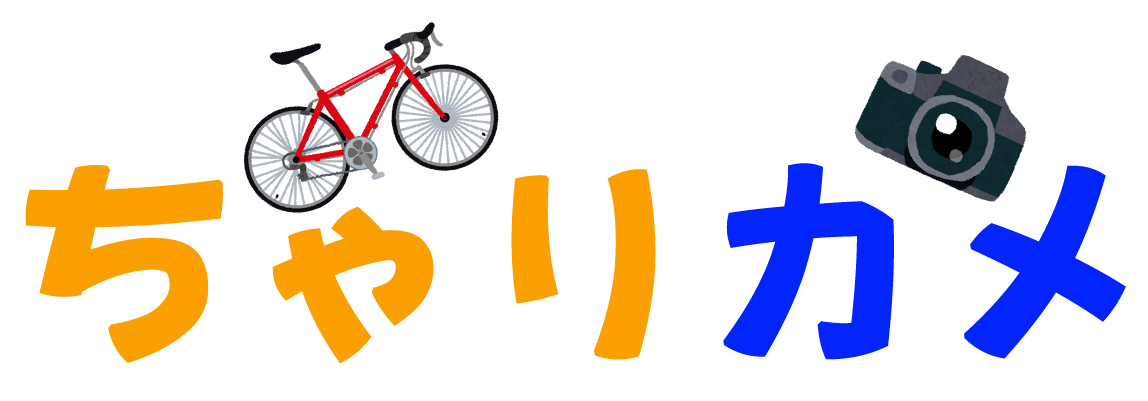












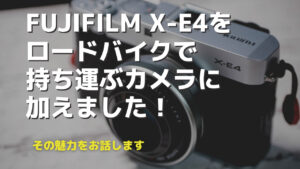
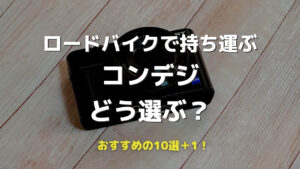

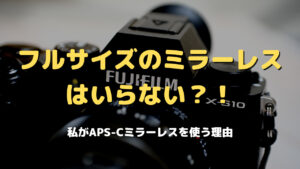
コメント